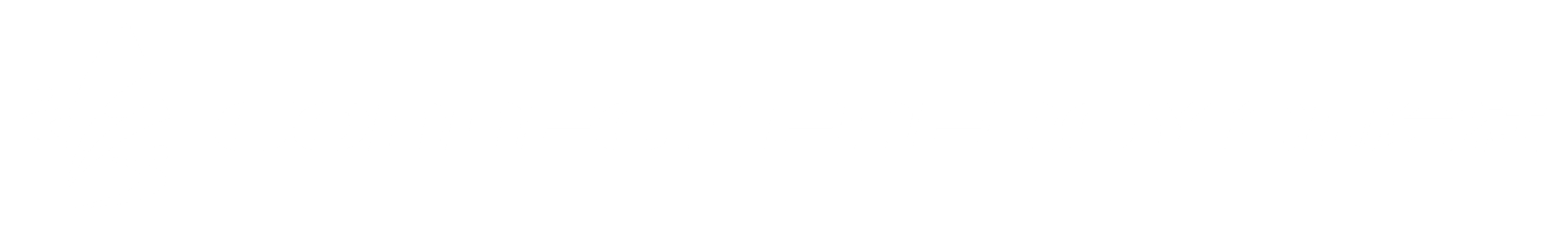2025年2月号
-事業者の皆様に私(境野)ができること-
*****************************************
みなさん、こんにちは😄境野です。本メールは、私が今までお会いしましたガス事業者様にお送りしております。
LPG商慣行是正講演が70回を超え、多くの事業者様の声を聴く中で、「何かもっとお役に立てないだろうか」「事業者の方々を自分なりにお支えすることはできないだろうか」-そんなことを考えているうちに、「またメルマガを始めよう」と思い至りました。
思い返せば、ENEOSにいた時もイーレックスにいた時も、メルマガが多くのお客様にお読み頂くようになって、その時々で喜んで頂き、人と人を繋ぐことになったりしたわけで、やらない手はないな!ということで始めます、また今日から😄
※一昨日、Gmailアドレスで一度お送りしましたが、迷惑メールになっている可能性が高く、私のプライベートアドレスで再送させて頂いております。
*****************************************
※不要な方、加えたい人がいる方はその旨、ご返信ください。対応いたします!
_________________________________________
今月のコンテンツ
🟦LPガスコーナー
🔴日置さんからの依頼
🟠消費者契約法について
🟦エレトクコーナー
🔴エレトクって何なの?
🟠エレトクはどういうところにおすすめ?
🟦雑感コーナー
🔴橘川先生との対談~その1
📖今月の書籍
__________________________________________
🔴日置さんからの依頼
経済産業省の流通政策室、日置室長と最近やり取りをしている中で、2つほどお願いを受けました。
一つは、「商慣行改革に取り組んで良い成果を挙げた実例」について、です。既に次回ワーキング(2月下旬開催予定)に間に合うように、先行して代表事例をお送りさせて頂きましたが、良い事例があればどんどん挙げていきたいと思っています。皆様方で「従業員のモラルが向上した」「売上は減ったが余計な経費が減った」等など、良き事例がございましたら遠慮なくお知らせください。
二つは、「消費者への強引なLPガス勧誘(その後、大幅な値上げにつながると予測される安値売り込み情報含む)については、液石法の通報フォームに情報を寄せて頂いても即効性がなく、特商法の情報提供窓口に持ち込んで欲しい、というものです。流通政策室、少ない人数でガソリンの補助金までやっておりますのと、やはり即効性の観点からは特商法窓口がよいかと、私も思います。
○特商法に基づく申出制度についてのパンフレット(3ページ目に、迷惑な勧誘行為や、事実と反することを言う行為も規制対象と明記されています)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230809ac01.pdf
○特商法違反被疑情報提供フォーム
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/
🟠消費者契約法について
これ、去年4月19日の「中間とりまとめ(案)」のパブリックコメントの「24」にあって、ずっと気になっていたんです。

「いわゆる貸付配管について、消費者がLP ガス事業者を当社から他の事業者に切替えた際に、14条書面のとおり貸付配管の残存分の代金を請求し、入金されたが返金請求されるなど裁判になった。裁判官に、液石法にしたがって貸付配管の代金を請求しているのになぜ裁判になるのかと尋ねたところ、消費者契約法で主張されると争いになるとのことだった。法改正時、消費者契約 法、液石法、民法等の考え方から、LPガス 事業者が生き残れる方策を検討してほしい」
-弁護士の松山先生にお聞きしたところ、「消費者契約法は消費者と利用者の情報量および交渉力に「構造上の格差」があることに鑑みて、消費者がその内容を正確に理解していたとしても無効とするものなので、LPガス事業者が消費者に対して無償貸与や貸付配管の契約内容を詳しく説明し、消費者の理解を得たことを理解する措置を取ったとしても、その内容によってはその条項は無効となります。
したがって、貸付配管のことが契約書に小さく書かれているだけで、消費者が確実に理解しているとは言えないような状況であれば、貸付配管の条項は無効であり、それまで支払った配管代の返還請求か可能となる可能性があります」-とのことでした。
要するに、消費者に不利益が及ぶ、あるいは知り得ないであろう内容について、「契約書に書いてあるでしょ」では通らないのがこの消費者契約法なわけです。14条書面の再交付は「義務」ではなく「推奨」ですが、できればこの機会を通じて消費者に丁寧な口頭説明をしていくのが望ましいと思います。問われているのは、「説明責任」ですから。
__________________________________________
🔴エレトクって何なの?
はい、私がいま一押しの製品であります🎉

空調の室外機に取り付けて、圧縮機の運転を制御、電力使用量を最大25%程度減らしてしまうという優れもののデバイス。空調って、法人施設の電気代の3割から4割ぐらい占めてるんですよね。照明よりも電気、使ってるんです。
最大の特徴は、「初期投資もランニング費用も掛からない」点、そして「リアルタイムな電流値測定による正確無比な削減量(=削減料金)の算定」にあります。
「初期投資無料❗」と言うと、「え~、嘘でしょ😅」との反応もございますが!正確に算定した毎月の削減額の中から一部を回収させて頂くビジネスモデルとなっております。ですので、設備投資にお金を掛けずに、着実に電気代を減らしたいという、いまいまの法人様のニーズにピタリと当てはまる製品なんです。
🟠エレトクはどういうところにおすすめ?
やはり、空調をたくさん使うお客様におすすめです。空調が24時間稼働となりますと、病院や介護施設、冷凍冷蔵倉庫、それと大型の工場やスーパー、ホテルなどにも導入させて頂いております。
導入の目安としましては、「年間電気代が800万円以上」「容量が30kW以上(高負荷率)」となります。
「基本料金」「料金単価(夏季、他季)」「空調圧縮機の容量(KW)」が分かれば、「どれぐらい電気代が削減できるか」のざっくりとした試算が可能です。
「圧縮機の容量(KW)」は空調の銘板に書いてありますし、設備担当の方はすぐお分かりになると思います。で、「だいたい、これぐらい減りますよ」ということで、「よし!導入しよう」と決めて頂きましたら、現地を調査させて頂きまして、エレトクの必要設置台数や、より詳しい削減金額を試算させて頂きます。
※「圧縮機の容量って💦」-分からない、分かりづらい場合、銘板の写真を撮って送ってください❗
__________________________________________
🔴橘川先生との対談~その1

現在、プロパン産業新聞にて隔週でコラムを連載しておりますが、橘川先生→境野→橘川先生→境野・・という順で、私の方はお陰様でもう連載100回を超えまして🎉もうすぐ丸5年になります。今回、新聞社の企画で新年特別対談という形で行わせて頂いたのですが・・・先生はとても気さくな方でした❗ご自分で、「私は学者というより運動家なんです」と仰られていたように、商慣行是正の実現に向けて、色々と戦術を練っておられます。
ワーキングでは歯に衣着せぬ論調で、鋭く大手事業者に切り込まれておりました。特に印象に残っているのが、第5回でしたかね。某委員の発言に対して、
「賃貸への過剰投資はしないと言うが、三部料金制は問題があると言われた。法律で決めることもおかしいというようなことも言われた。私は両方、間違っていると思います」
「三部料金になっていないからこそ転嫁が起き、賃貸のところに消費者の不利益が生じている。林委員は「消費者被害と言っていい」とも言われた」
「そもそも、今まで指針と行政指導だけではなかなか進んでこなかったところに問題があるわけで、それを今さらもう一度、行政指導と指針の徹底でいきますというのは、全然、消費者に対する答えになっていない」
・・・ここで三部料金の義務化が、事実上、決まったわけですね。流石でした。
📖今月の書籍
土曜日の日経で『失敗の本質(野中郁次郎氏他)』に触れていたので。私もだいぶ前に読みましたが、旧日本軍の失敗がバブル崩壊の原因と重なって非常に興味深かったのを覚えています。「一言で言えば、成功体験への過剰適応」との言どおり、高度経済成長期のプロセスをそのまま追った結果、バブルで自壊して30年の低迷を招いた日本経済。
失われた30年の元凶は何か、とコメンテーターが聞いて野中氏から返ってきた答えが、「プランニング(計画)、アナリシス(分析)、コンプライアンス(法令順守)の3つの過剰こそ真因」との言。
さらに野中氏は、「PDCAがPdCaになってしまった」と指摘。「Pの計画とCの評価ばかりが偏重され、dの実行とaの改善に手が回らない」と。これ、ENEOSなんていう大企業にいたからよく分かるんですよね。経営企画部みたいな管理部門がやたら大きくなって、計画と評価は立派で時間も掛けるんだけど、肝心な実行力が手薄で、実行してないから改善もしようがないぞ、と。
大企業の多くがビジネスモデルが確立していて、極端な話、何もしなくてもお金が入ってくるものだから、これがまかり通ってきました。しかし、これからはもう無理ですね、これだと。逆に、中小企業は「pDcA」じゃないと潰れてしまいます。計画と評価はそこそこに、何よりも実行と改善、このプロセスの繰り返しこそが成長への礎となります。
とにかく、失敗してもいい覚悟で、何でもまずはやってみること。成長企業とそうでない企業の差はここです。「理解している、やれば出来ることも分かっている、だけどやらない」…ダイエットみたいですね🤣とにかく、やってみましょう。
以上
************************************************************