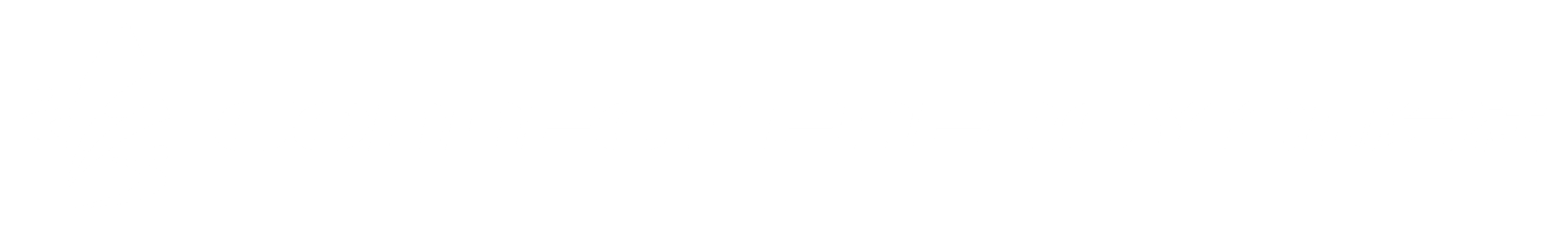お盆で群馬に帰省してまして、83歳の母親がこう話してくれました。「あの頃は本当に貧しくて、8人も兄弟がいたのに、全員、高校に出させて、男5人は大学にまで行かせてくれた。貧しい中で相当な苦労だったと思う」と。
戦後まもなくのことですから、焼け野原の中、物資はないは食料はないわ、そんな中で子供を高校に行かせる家なんて、近くになかったそうです。そのお陰で今の自分がいると思うと、感謝に堪えないわけですが。
まあ、そんな身近な戦後の体験談とか、今後、聞く機会が無くなっていくことを思うと、しっかりと戦争の様々な記憶や経験を学習しておくべきなんだなと、思いを新たにした次第です。
なぜそう思うかというと、ロシア・ウクライナにおけるアメリカの振る舞い方なんですね。
「トランプが『領土交換』とか持ち出して、関税ディールさながらのやり取りを、ウクライナの頭越しに勝手に進めるんじゃないか」との懸念を、当初、国際社会は持っていました。
しかし、この問題に関してはさすがにトランプも、いやむしろ取り巻きがより慎重だったのではと思います。
なぜなら、ロシアの『占領した土地を割譲せよ』の案を停戦条件として呑めば、端的に言えば
主権国家への不法な侵略行為を認めることになる
からです。中国が台湾を武力で併合して国際的な非難を浴びたとて、「ロシアは承認したじゃん」と言われれば何も言えなくなる。
だからこそ、国際社会は一致団結してウクライナ領土の割譲など、断固として認めてはならないのです。
この問題、日本政府はもっと危機感を持つべきなんです。仮に北海道にロシアがミサイル攻撃を仕掛けて、札幌市内が瓦礫の山で埋め尽くされ、「停戦の条件は北海道の割譲」と言われて「はい、分かりました、どうぞ」と言えますか?
「そんなことは起こらない」なんて言わないで下さい、現代では起こりえないはずの侵略戦争が現に起こってるんですよ。
旧ソ連は80年前、終戦間際に日ソ不可侵条約を破って南樺太と北方領土を掠め取り、自国の領土としましたが、これは明らかに国際法違反です。
だからこそ「返せ!北方領土」という一大キャンペーンがかつて張られていたのですが、それも下火になってしまった感があります。
イラク戦争の時は多国籍軍が形成されて、クウェートに侵略したイラクを懲らしめたのに、同じ行為をしたロシアにそれが出来ないのは、大国であることに他ならないのでしょう。
が、ここで世界が弱気になってはならない。いかなる理由があっても主権国家への不法侵略は許してはならないのです。
難しい問題ではあるものの、ここは世界各国が「自国ならどうする」ということを念頭に置いて、粘り強く、そして力強く、国際社会の秩序を守って頂きたいと思います。
それが戦後80年、日本全体が思いを強くすべきところなのではないでしょうか。